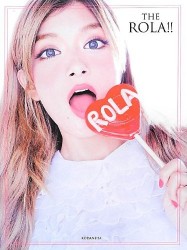おいちゃんは東京で生まれて野島伸司で育ったので、今も毎週『高嶺の花』というテレビドラマを観ている。意味もなく唐突に「たぁぁぁぁぁかねの花よ!」と石原さとみちゃんの真似をして家族に鬱陶しがられている今日この頃です。
野島伸司のドラマはいつもその時代の世相や色あいを見せてくれる。浮かれた時代には底抜けに明るい色恋ものを、平和ボケした時代には後ろ暗くあさましい人間の闇を、閉塞した時代には心温まる絆の物語を、というように、時代の温度に合わせたり、あえて真逆をとることで、その世相を作品に反映してきた。
テレビドラマっていうのは常にそのように時代の潮流を汲み取らざるをえない表現であって、さらにそこで独創的な作家性をめいっぱい発揮できるのが、野島伸司がヒットメーカーでありつづけられる所以だ。
野島作品を見ていると、テレビドラマというのは映画とコミックのちょうど真ん中あたりに位置するのだなとつくづく思う。映画ほど現実に寄りそっていない、漫画ほどファンタジーでもない、ドラマだからという必然的な立ち位置。
さて、放映中の『高嶺の花』が表す現代の色あいや温度っていうのはどういうものだろう。
混沌。多様性。イミテーション。普遍。聖なる存在。
僕の頭に浮かぶイメージの断片はそんなところだ。チープなイミテーションと普遍的な何かが、箱庭の中でせめぎあって、ごちゃごちゃやっている、そんな風景。それはまさに今の世相を映しているような気がするのだけれど、人間がやっていることなんていつの時代も同じだというような気もする。いつだって、混沌があって、対立があって。
まあ、まだ終わってないのでよくわからないんだけどさ。なんだか野島伸司自体が混沌としているのではないかという印象だけれど、クライマックスではきゅっと気持ちよくまとまったところを見せてくれるのかもしれない。いや、野島がそうやすやすと気持ちよくしてくれるとも思えないけれど。
はっきり言って、引きこまれるほどおもしろいドラマ、というわけじゃない。それでもとりあえず毎週見てしまうのは、何がかろうじて僕をテレビの前に引き留めているかといえば、石原さとみちゃんの可愛さ以外には、ひとつにお家元の存在がある。
小日向文世が演ずる華道の大家、神のように崇め奉られる芸術家は、自らの核心に何を持ち、その脳裡にはどのような絵図を描いて生きているのか、僕の知らない何を見せてくれるのか、というような興味が僕を引き留める。
あるいは峯田和伸演ずるプーさんという〈聖なる存在〉が、芸術に魂を売った悪魔と天使、その下僕たちにどう立ち向かい、彼らをえいやっとやっつけるのか、それとも無情にも屈するのか、あるいは勝ち負けとは関係のない着地点に達するのか、という対立にも惹かれる。
だんだん物語が大きく動いてきて、さらに興味深い登場人物が増えるようだから、なんだかんだ楽しみになってるみたいだ。
石原さとみ演ずる華道家・月島ももは、〈罪の意識〉と引き替えに芸の術を手に入れようとする。僕自身もここ数年、〈罪〉を主題にあれこれ考えているので、その辺の行く末にも期待したい。