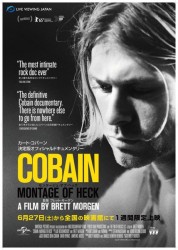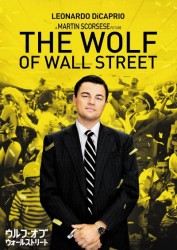ぼくはiTunesで買ったけど、今ならNETFLIXでもAmazonプライムでも見られるので、ぜひ週末にでも見てちょうだい。
年をとると時代劇を見るようになるのはあれ何なんだろうとずっと思っていたんですが、ひとつには、年を重ねて人生の酸いも甘いも生き死にも見えてきて、視野が広くなると、自分のルーツにつながる過去の時代にリアリティが出てくるからなんじゃないでしょうかね。
現にぼくも、本作で描かれる、そこらへんで人がいきだおれになっているような死と隣り合わせの時代、女が蔑まれていた時代が、決して絵空事ではなく、ぼくの命をつないだ先祖が生きた時代であるのだと、胸がぎゅっと締めつけられるんですもの。
ぼくがこの作品を推す第一の理由は、映画としてとてもおもしろいこと。
うん、そう、当たり前なんですが、エンターテイメントとして完成されている、という、映画の土台がしっかりしているから、ちゃんとそこで伝えたい重苦しいものが、観客に届くんですね。つまり堅苦しくヘビィな時代劇じゃないよってことです(これからうだうだ書いてるけど、そういうの抜きにしても笑えて泣ける楽しい映画ですよってことです)。

主演が大泉洋さんですから、まあそこは想像つくかもしれないけれど、これだけの奥深い物語をコメディとしてこしらえた原田監督は偉大です!ユーモアはもちろんあるものの、コメディアンではなく一人の役者としての大泉洋さんがまたとても素敵。作中の言葉を借りるなら「素晴らしくて敵わない」のです。
けれど、本作の本当の主役は大泉さんではなく、旦那に殴られ蹴られこき使われる練り鉄のじょご(戸田恵梨香)や、唐物問屋の妾のお吟(満島ひかり)をはじめとした、東慶寺に駆け込む女たちです。
当時、夫は勝手に離縁(離婚)することができたけど、奥さんは旦那がどんなにひどい男であっても、自分から別れることができなかったんですね。いつの時代もだいたい男というのは馬鹿ですから、図に乗って女をつらい目に合わせるのがのさばっていて、さすがにそれはあまりに不憫だというので、鎌倉の東慶寺に駆け込んで事情を認められれば、二年の入山の後に、離縁できるという制度が生まれたそうです。とはいえ、駆け込み寺は鎌倉の東慶寺と群馬県太田市の満徳寺の二つしかなかったそうなので、遠方には駆け込むことすら叶わない女たちがたくさんいたのだと想像できます。

そもそも封建時代というのは本当にめちゃくちゃで、漁師の娘を手篭めにしようとした武士の刀を父親が奪って斬り捨てれば、漁師が武士を殺すのは大罪だということで死罪。娘は舌を焼かれ、母は狂い死ぬ、なんてことが平然と行われていた。歴史の教科書ではあまり教えてくれない、時代の生々しさとか痛ましさを、こういう映画が伝えてくれるわけです。
東慶寺を治める院大様が、入山する女たちにかける「よく息を詰まらせず生きてきました(=今日まで死なずによく頑張って生きてきましたね)」という言葉に胸が熱くなります。
身分の低い生まれのじょごは徹底的に自己肯定感が低く、いつも自分を蔑み、あとまわしにしますが、士農工商の封建社会においては、限られた武士や貴族以外は、みんなお上から「おまえたちは卑しい身分なんだよ」と扱われていたわけですから、じょごみたいな女がふつうだったんでしょうね。そう考えると、昨今自己肯定感だとか自己否定だとか心の理が分析されていますが、そのルーツがこの身分制度にあるのだとしたら、「世の中だいたいが町民農民の出なのさ」とひねくれて唾でも吐きたくなってきます。
お吟は問屋の旦那の妾、と言っても女将さんとして商いを仕切る、ほぼ正妻のような立場でしたから、気位は高く堂々としていますが、当時は治療法のなかった労咳(結核)を患ってしまいます。
飢饉があればそこらへんでいきだおれて死に、結核で死に、戦で死に、不条理に武士に斬られて死に、貧しくて死に、道端のどこを見やっても「死」ばっかりの時代。そんな時代が本当にあったんだなあ、そんな時代を先祖が生き延びてくれたから、今ぼくはこうしてぬくい部屋で猫を撫でながらiPhoneで遊んで子どもたちと笑っていられるんだなあと、やはり胸が熱くなります。
ぼくはいつも、この作品を見ると、勇気と元気をもらうんです。
ぼくの今生きているこの時代、この環境は、なんて素晴らしいんだって。テレビのニュースキャスターも政治家もネットに文章を書く人も主婦もビジネスマンもそしてぼくも、みんな深刻な顔をしてしかめっ面であれこれ糾弾したり文句言ったり悩んだりしてるけど、こんなに素敵な世界に生きていて、何を言っちゃってるんだろうって。
想像妊娠をしたおゆきという女を、大泉洋さん演じる医者見習いの信治郎がみんなの前で説得して治療するシーンがあります。あれは今で言うところの心のオープン・カウンセリングみたいなものなんでしょうが、あのやり取りの中に、原田監督の熱いメッセージが込められているように感じました。

想像妊娠で腹が「痛い」と泣くおゆきに「痛くない」と叫ぶ信治郎。
痛い、痛くない、痛い、痛くない、痛い、痛くない、痛くない痛くない、本当は痛くない、痛いと言い聞かせてるだけなんだよあんたは!嘘の痛みで、自分を罰することはないんですよおゆきさん!
ぼくもカウンセリングというか人生相談みたいなことをやっていましたが、おゆきさんと同じように、罪悪感に苦しんで、自分で自分を責めて、嘘の痛みで自分を罰している人がたくさんいました。ぼく自身がそうであったからよくわかるんだべさ。
けれど気がついてほしい。本当は痛くないって。自分を罰する必要なんてない。ありのままの自分を許していいのだと。

駆込み女で描かれる江戸時代は、実際にそこに住んでみたら、もう本当に悲惨な時代です。蔑まれ、痛みを与えられ、いつ死んでもおかしくない、そんな毎日だからこそ、気高く、粋に、あだっぽく生きようとする人々の姿は凛と美しく、己の無粋、ダサさが身に沁みます。ぬるいのう、俺はとことんぬるいのう、と。
「駆込み女と駆出し男」は、きびしさとやさしさが同居した映画です。本当は戯作者(小説家)になりたいのに、自分を曲げて医者の道を進もうとする信治郎に、じょごは言います。
「いつか書く戯作の準備はじゅうぶん!風の道は通っております!あとは死に物狂いでふいごを踏み続ける、だけです!」
いつまでも自分を罰したり、自分から逃げたり、世界を嘆いてばかりいないで、さっさとやりたいことをやりなさい!ってことですね。死ぬ気でやれよ、死なないから。
じょごの言うように、風の道は通っているんです。あとはそこを進むかどうかだけ。
さてぼくも、強味と渋味はちょんぼしだけど、素敵な男になるために、死に物狂いでふいごを踏み続けていく所存でございます。