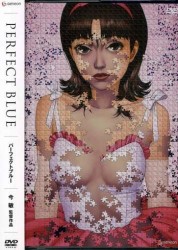先日のアカデミー賞授賞式にて、作品賞受賞かとぬか喜びしてドヤ顔でスピーチまでしちゃったらじつはプレゼンターが間違ったカードを読み上げちゃってて違う作品だった、という前代未聞の大珍事もあって、いろんな意味で話題の「ラ・ラ・ランド」。若者が思っているほど大衆受けする大ヒット作のタイプではないし、かといってオスカーをもらうほどオカタイ映画でもない、という感じで、個人的には至極のエンタメとしてブスリと心に刺さった、というのが率直な感想。
よくできた予告編を見て、あとあの衝撃を受けた「セッション」の監督作品でアカデミー最有力とかベネチアとかゴールデングローブとかの傑作の看板になる言葉がたくさん付随してたので、ずいぶん期待して、中学生以来なんじゃないかな、公開初日の朝一の初回上映に出向いちゃって、なかなかハードルが上がってたんだけども、それだけ期待していた分、いざ始まってみると、大事なつかみをどう持ってくるんだいチャゼル監督!ってワクワクしてたら、冒頭の排気ガスと熱気でむんむんしているL.A.の高速道路の渋滞のシーンで、いきなりまさかの怒濤のミュージカルがスタート!あっけにとられる間もなく歌とダンスに圧倒されて、オープニングタイトルがドドドーン!と画面いっぱいに出たときには、もうすでに立ち上がって拍手をしてしまいたくなっていたよ。実際ベネチア映画祭ではここで大拍手が起きたって後で知って納得しましたです。
理屈抜きに心を高揚させる(あるいは寒々しい)ミュージカルという魔法
ミュージカル映画って自分から率先して見たことはあんまりなくて(シカゴとかバーレスクとかジャージー・ボーイズくらい)、あとタモさんがミュージカル嫌いを公言していたので、なんとなく日本人には合わないのかなあなんて思ったりもしてたんだけど、このオープニングだけで体幹の隅々に鳥肌が立って、知らぬ間にニヤニヤニコニコしながら自分の身体が揺れていることに気づいたので、どうやらぼくにはミュージカルを楽しむ素養があるらしい、と確信しました。
ということで、このオープニングのエッセンスを詰め込んだ予告編でワクワクできたら、あなたもきっと最後まで楽しめますラ・ラ・ランド。今さら言うけどもちろん一番楽しむ方法は、こんなくそみたいな文章やネットのレビューとか一切見たり読んだりしないで、目を閉じて耳をふさいで体調を整えてトイレを済ませて今すぐ劇場の闇に身を潜めることですよあしからず。
話を戻すと、ミュージカルっていきなり歌って踊り出すから恥ずかしいとかいうのもわかるけど、まあたしかに日本人だとあまりにいきなりで寒々しいのかもしれないけど、ゾンビと一緒で、やっぱり欧米人の迫力というか勢いというか他人事的雰囲気が圧倒してくれるので、この映画なんかはじつにスムーズにミュージカルシーンが展開されます。まさに現実と並行する夢の国、ララランド。それどころかキュートなエマ・ストーンも他の役者も、歌と踊りでその魅力が倍増しているように見えちゃうもんね。
かつてまだ電気アンプリファイアの技術が無かった時代に、オーケストラがなるたけ多くの楽器を動員してその音の重なりと音量で聴く者を圧倒したように、ミュージカルにも歌とダンスで人を理屈抜きにぐいぐい高揚させる力がある。「なぜかわからないけどなんだか昂(たか)ぶるわ!」っていうのがミュージカルの魅力であり、かたやそれが刺さらない人には寒々しくてしょうがないのだろうけども、チャゼル監督のクールな演出と現代の技術で、そんな寒々しさも感じられない完成度な気がします。
エマが挑発的な表情で腰とスカートの裾を左右に振りながら歩く振り付けとか、ミュージカル特有のキュンキュンさせるあの表情とか振り付けって魔法は心理学的に何かあるよねきっと。
夢を成し遂げるのには、すこしの「狂気」がいる
さて、映画ってのはときにシンプルで月並みにさえ見える愚直なメッセージを、物語やキャラクターや映像や音楽でぶっとい槍に変えて観る者の心に刺す表現だから、物語を説明することほど不毛なことはないんだけれど、それでも無粋を承知で書いてしまうと___、本作も前作の「セッション」においても、デイミアン・チャゼルが描きたかったのは、人生と芸術、現実と夢をどう調和させるか、っていうお話なんですね。芸術との関係と、人間との関係をどうしましょうかーっていう物語で、それはぼくらにしてみたら、夢や仕事と人間関係をどう調和させたらいいのか?っていうテーマに置き換えられる。
つまりよくある「仕事と私のどっちが大事なの?」的な、夢(仕事)と恋人のどちらを選ぶか、っていう究極の選択のひとつの答えが、この映画に込められている。究極の選択と言えば、家族が溺れたときに、奥さん(または旦那さん)と子どものどちらを助けるか?っていうあれも究極だよね?あなたならどうする?ぼくなんか想像しただけで卒倒しちゃいそうで答えられないから、やっぱり両方助ける、ってところに逃げ込みたいけど、そうもいかないんでしょう。ラ・ラ・ランドの展開でも、二人が追いかける夢が困難で狭き門だから、やっぱりどっちか一方、夢を取るか、恋人を取るかっていう二者択一になっちゃうんだけども。
そういう葛藤も含めて、チャゼル監督がポップなエンターテイメントの中で描いたのは、極めてシンプルに「夢を追う者たちの物語」。そして「セッション」から一貫しているのが、夢を叶える、なにかを成し遂げる、新しい世界を見るのには、ある種ある程度の「狂気」が必要だよ、というテーマ。
本作のミア(エマ・ストーン)とセブ(ライアン・ゴズリング)が目指す映画女優にジャズ・ミュージシャンっていう狭き門って、そこを通って成功する人はもちろん、成功しないその他大勢、そんな「夢みたいな」「一部の限られた才能のみに許される」世界を目指すことでさえ、よく考えてみたら、はっきり言って、狂ってる、と言えなくもない。
スポーツ選手だって小説家だって芸人だって何だっていいんだけど、その他大勢からぬきんでて成功する人って、本当に狂ってるんじゃないかってくらい、自分のやることに没頭してるじゃないですか。本田圭佑が朝から晩までサッカーのことしか考えないように、手塚治虫が死の直前まで病床で漫画を描きつづけたように、みんな、常人と比べたら、そりゃあもう、狂ってる!もちろんチャゼル監督も。
若いうちはまだいいけど、だんだん年を重ねて残された時間の幅が感覚でわかるような頃になると、いつまでも夢を追いかけている人って、ミアがラスト近くで歌うすんばらしい挿入歌の歌詞を借りれば、惨めで、愚かで、厄介な人じゃないですか。「ハリウッド女優目指してる?おまえちょっと頭冷やせ」ってなるでしょう。
けれど、それでもね、たとえ愚かに見られても、夢を追う人を応援したくなる、そんな気持ちを内包した映画。もしかしたらぼくらが無意識にバカにしている人たち、夢破れた人たち、その道で成し遂げられなかった人たち、あるいは隠しているそんな自分、そういう人たちをね、笑えないよと、彼らの美しさにはかなわないよ、という気持ちになる。
だから、もしあなたが、くじけたりいじけたり泣いたり苦しんだりしながらも夢を追い続けているのだとしたら、ぜひラ・ラ・ランドを見て、自分は独りじゃないって勇気をもらってほしいと思うし、逆に、夢を追うんだ、と口にしながらも、なんだかんだ夢に向かう覚悟や準備ができていない人、夢という言葉を免罪符に使ってふらふら遊んでる人は、彼らの真摯さと狂気を目の当たりにして出直してきなさい。
ミアがオーディションで歌う、おばさんがセーヌ川に飛び込むっていう内容の歌が、夢を追うあなたの勇気になるはずです。おばさんはなんでセーヌ川に飛び込むのか知らないけど(夢に理由はいらない)、凍えるほど冷たい水に飛び込んで、身体壊して一ヶ月もクシャミして、それでもまた、飛び込むって言うんだ。何度でも、笑われても、馬鹿にされても。夢を追うって、そういう愚かさだよね、狂気だよねっていう、素敵な歌です。
ラストでセブが見た夢の意味
ラストでセブが見た夢___現実と違う妄想のようなシーンは、見ていて鳥肌が立った。これは決して妄想じゃなくて、理屈で説明できないけれど、これもまた現実だよな、という直感に打ち震えていたら、チャゼル監督が同じようなことを言っていて納得。とにかくとても美しくて切なくて。
ミアは何を選び、セブは何を選び、二人はハッピーエンドなのかそうではないのか、そこに物語の核心があるのだけれど、さすがに野暮なので言及するのはやめておくので、ぼくと同じように打ち震えた人はそのうちどこかでセロニアス・モンクでも聴きながらじっくりお話ししましょう。ラストが腑に落ちない、という人は、「狂気」について考えてみてください。死ぬほど愛し合った相手より夢を選んだ人を、あなたは人でなしと蔑(さげす)みますか?
あと、作家視点で付け加えると、このチャゼル監督ってのは、「自分が本当に愛してきたもの__ジャズと映画」と「自分にとって大切な人生のテーマ__芸術と恋」を、すべて、もったいぶらずに残らずすべてぶちこんでいるんだなあという感慨がありました。よく表現の世界で「今持っているものすべてを作品に込めろ」って言うけど、そういうことなんだなあと。セッションから本作、そして次の作品へ、表現やメッセージは変わっても、底に這うテーマや気持ちは、ずっと変わらないのかもしれない。そしてもしかしたら表現者っていうのは、ひとつの作品なんかじゃ伝えきれない衝動をずっと隠し持っていて、生涯をかけてそれを表そうとあがくのかもしれない。多くの小説家がけっきょく同じことを書きつづけるように、あだち充がいつも似たようなキャラを描くように。